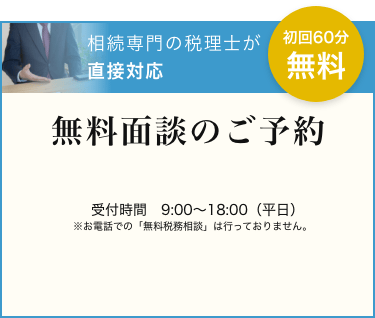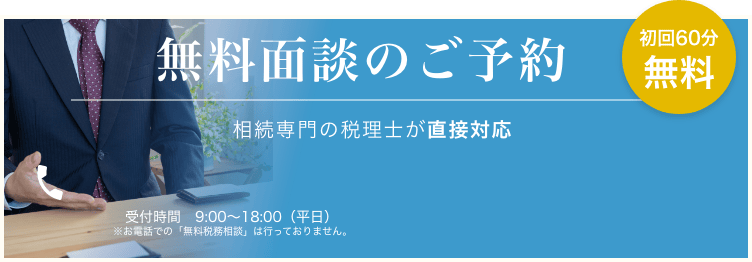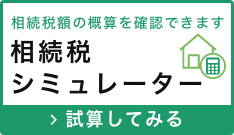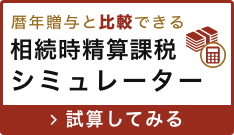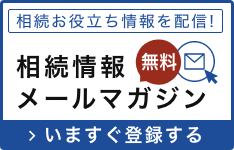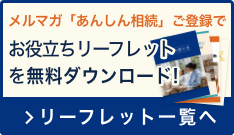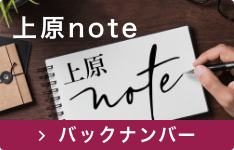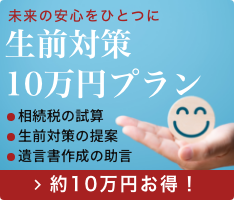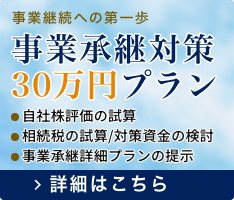目次
応援したい自治体に寄付を行い支援することで、地域の特産品など返礼品がもらえるほか、所得税や住民税の寄附金控除が受けられ節税にもなるのが「ふるさと納税」です。しかし、実は「ふるさと納税」は相続税の節税対策にもなることをご存じでしょうか。
ふるさと納税は自分の財産から自治体に寄付を行うことを基本としているため、直接的に相続税には関係ありません。しかし、相続税における「寄附金控除」という制度を活用することにより、相続税の節税を期待することができます。
ここでは「ふるさと納税を活用した相続税の節税方法」について詳しく解説いたします。
1.ふるさと納税で相続税対策する仕組み
ご存知の通り、相続税は亡くなった人(被相続人)から財産や権利を引き継いだ際に発生する税金であり、引き継ぐ財産の金額によって納税額が異なります。財産の中でも一部の財産は相続税が課税されない「非課税財産」が規定されており、墓地や仏具などの祭祀財産や弔慰金などのほか「公益団体や公共事業への寄付」についても以下の通り、非課税財産です。
7 相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
【出典】「No.4108 相続税がかからない財産」|国税庁
ふるさと納税は上記「公益団体や公共事業への寄付」に該当するため、ふるさと納税を利用して相続財産を寄附した場合は遺産総額から寄付金を差し引くことができ、その結果、相続税の軽減に繋がります。
1-1.所得税・住民税の寄付金控除と併用できる
相続税の節税のためにふるさと納税を行った場合であっても、ふるさと納税を行った相続人の所得税・住民税で寄付金控除を受けることができます。
ただし、所得税と住民税におけるふるさと納税の寄付金控除は、所得や家族構成などによって控除上限額が異なりますので、事前に検討する必要があります。
2.ふるさと納税を使った節税効果のシミュレーション
「ふるさと納税を活用することで、どれくらい相続税を節税できるのか?」を、以下の事例を使ってシミュレーションしてみましょう。
事例
- 被相続人:父(母はすでに他界)
- 相続人:子1人
- 遺産分割:全て子が相続
- 遺産総額:1億円
- 基礎控除額:3,600万円(3,000万円+600万円×1人)
2-1.ふるさと納税を活用しない場合
ふるさと納税を活用しない場合は遺産総額から基礎控除を差し引き、各人の相続税額を算出します。
1億円-基礎控除額3,600万円=課税遺産総額6,400万円
課税遺産総額6,400万円×相続税率30%-控除額700万円=相続税の総額1,220万円
2-2.ふるさと納税を活用した場合
200万円をふるさと納税した場合は、遺産総額から200万円を控除して相続税を算出します。
1億円-ふるさと納税200万円-基礎控除額3,600万円=課税遺産総額6,200万円
課税遺産総額6,200万円×相続税率30%-控除額700万円=相続税の総額1,160万円
2-3.相続税の節税になるが現金の支出がある点に注意
上記のシミュレーションでは、ふるさと納税を活用しなかった場合の相続税は1,220万円、ふるさと納税を活用した場合には1,160万円となり、ふるさと納税を活用することで相続税額を60万円節税することができました。
また、相続人の所得税と住民税の寄付金控除に加えて、自治体からの返礼品を受け取ることもできます。
ただし、ふるさと納税として合計200万円支出しているため、相続人の所得や家族構成を踏まえ、総合的に見て節税になっているのかどうかをケースバイケースで判断する必要があります。
3.ふるさと納税に相続税の寄付控除を適用させる要件
相続人がふるさと納税を行ったからといって、自動的に相続税の寄付金控除が適用されるわけではなく、相続税の寄付金控除を行うためには次の要件に合致しなければなりません。
3-1.相続税の申告期限までにふるさと納税を完了させる
相続税の寄付金控除としてふるさと納税を活用するためには、相続税の申告期限である相続開始を知った日の翌日から10か月以内にふるさと納税を完了させる必要があります。
公益法人などへの寄付については「その取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること」と定められています。申告期限までに相続人全員で遺産分割協議を完了させ、相続した現金預金からふるさと納税を行わなければなりません。
申告期限を過ぎてからふるさと納税を行っても、相続税の寄付金控除の対象外になってしまいます。
3-2.申告書第14表を提出する
ふるさと納税で相続税の寄付金控除を受けるためには、相続税申告書の第14表に記載が必要になります。
ふるさと納税により寄付した日付や財産の明細を記載し提出しましょう。
3-3.寄付金受領証明書を申告書に添付する
申告書第14表とともに寄附金受領証明書を申告書に添付する必要があります。寄附金受領証明書とは、ふるさと納税をした際に寄付した自治体から送付されてくる書類です。
この証明書はふるさと納税を行ってすぐに発送されるわけではなく、寄附の完了後1~4週間後になるのが一般的です。申告期限に間に合わせなければなりませんので、早めにふるさと納税を行うようにしましょう。
4.ふるさと納税を活用した相続税を節税する際の注意点
ふるさと納税を活用して相続税の節税を検討する場合には、次のポイントに注意しましょう。
4-1.遺言書でふるさと納税しても寄付控除の対象外
ふるさと納税で相続税の寄付金控除を受けるためには、相続人自身の意思で寄付を行う必要があります。
そのため、被相続人の遺言によりふるさと納税を行った場合には、寄付金控除の対象外です。
4-2.ふるさと納税には控除上限額がある
ふるさと納税を活用した相続税の節税は、相続税以外に所得税と住民税の寄付金控除による節税と自治体からの返礼品をも考慮しなければ損得が分かりません。
また、ふるさと納税による所得税と住民税の寄付金控除には上限額が設定されており、寄付額が多ければいいというものではありません。
ふるさと納税を行う相続人の所得や、家族構成による控除上限額をしっかりと押さえ検討しましょう。
4-3.相続人が相続財産を換金して寄付したら寄付控除の対象外
公益法人などへの寄付については「その取得した財産(現預金や生命保険金)を寄附すること」と定められており、例えば、相続した土地を換金してふるさと納税を行っても、相続税の寄付金控除の対象外です。
相続した財産をそのままの状態で寄付する必要があるため、相続した現金や預貯金、生命保険金からふるさと納税する必要があります。
4-4.ふるさと納税の返礼品とその他の一時所得の合計が50万円超にならないようにする
ふるさと納税での返礼品は所得税の対象になり「一時所得」に該当します。
ふるさと納税の返礼品とその他の一時所得の合計が50万円超になった場合には確定申告が必要になり、所得税と住民税が発生する可能性があります。
4-5.ふるさと納税で相続税がかからなくても申告が必要
相続税の寄付金控除を受けるためには、ふるさと納税を行った証拠である寄付金受領証明書の提出が必要になるため、たとえ寄付金控除を受けることで相続税がかからなくなっても相続税申告書の提出が必要です。
4-6.ふるさと納税は個々の事情を踏まえて検討が必要
ふるさと納税による相続税の節税は、ふるさと納税として自治体への寄付を行わなければなりません。相続税が節税でき、相続人の所得税と住民税が軽減されるからといって、寄付した以上に恩恵を受けられるとは限りません。
相続税の税率が高く、相続人の所得が高額である場合には、ふるさと納税を活用した方が有利になる可能性がありますが、事前にしっかりと検討が必要です。
5.相続税の節税をご検討の方はご相談を
ふるさと納税は、所得税と住民税だけでなく、相続税の節税対策として活用できる場合があります。ただし、寄付を行う相続人の所得や家族構成などを考慮し、いくら寄付を行えば有利になるのかを検討しなければ不利な結果になってしまうおそれがあります。
ふるさと納税を活用した節税対策を検討される場合には、相続税に強い税理士事務所に相談し、シミュレーションを行いながら進めていくことをおすすめします。
当事務所では、相続税のシミュレーションを使い、ふるさと納税で節税することが適切かどうかをアドバイス差し上げることが可能なほか、その他の適法で効果の高い節税方法をご紹介することもできます。
ふるさと納税の活用を含め、相続税の節税をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。