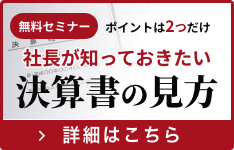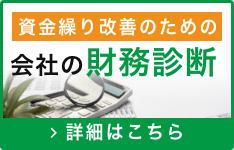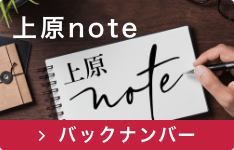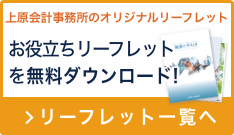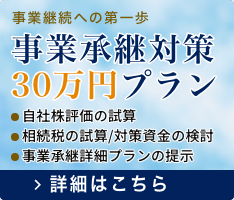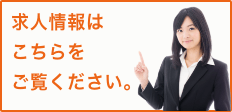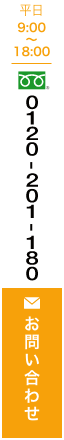目次
適切な対策を行っておかなければ納税資金が足りなくなってしまうケースも珍しくなく、会社の経営者や後継者にとって相続税の負担は大きなお悩みでしょう。
生前に相続税対策を行う場合でも、準備する前に突然相続が発生してしまうなど、予期せぬ状況により相続税が払えないケースも考えられます。
ここでは「自社株式の相続で相続税が払えない場合の対処方法」をご紹介いたします。自社株式の納税資金対策についても触れていきますので、最後までお付き合いください。
1.自社株式の相続税が払えないケース
相続人である後継者が自社株式を相続した場合に相続税を払えないケースには、次のような場合が考えられます。
1-1.相続税対策が不十分
生前に相続税対策を十分に行っていない場合には、納税資金が不足してしまうことがあります。
自社株式の相続税対策は、評価額を下げる対策を行い、下げたタイミングで自社株式を贈与する方法や死亡保険金の非課税枠を利用した方法や、死亡退職金を支給するための「役員退職慰労金規程」の作成などがあり、生前から相続税対策を行うことで、後継者が相続税を払えないといった事態を回避することができます。
1-2.自社株式の評価が高額
自社株式が非上場株式であれば、上場株式とは違い、取引相場がないため税法で定められた方法によって相続税評価額を算出します。
会社の業績が好調で利益を積み上げている状況であったり、含み益のある資産を保有していたりすると、自社株式の評価額が思っている以上に高額になってしまうケースもあります。
自社株式の評価額が高額になると、相続税の負担が増加し、自社株式を相続する後継者が納税できなくなってしまうケースも考えられます。
1-3.個人資産が多い
先代経営者の個人資産が多いケースでは、相続税の負担が高額になります。
財産の中でも預金の割合が多ければ問題ありませんが、不動産などの換金性が低い財産が多い場合は、納税資金が足らなくなってしまうこともありますので、自社株式以外にどれくらいの個人資産があるのかを把握する必要があります。
1-4.財産のほとんどが自社株式である
先代経営者の個人資産のほとんどが自社株式である場合、自社株式は現金化することが難しいため納税資金不足に陥ってしまいます。
会社が役員死亡退職金を支給できるようにするなど、納税資金を工面する対策が必要になります。
2.自社株式の相続税が払えない場合の対処法
自社株式を相続する際に相続税が支払えない場合には、次のような対処法が有効です。
2-1.会社に自社株式を売却する方法
相続後、相続人である後継者が自社株式を会社に売却する方法、いわゆる「金庫株」や「自社株買い」と言われる方法は納税資金対策として効果的です。
後継者が会社の株式を100%所有していれば、自社株式を会社に売却しても所有する割合は100%のままになり、会社の支配権はそのままで資金調達を行うことができます。
ただし、会社に自己株式を買い取る資金がなければ自社株式を買い取ることができません。先代経営者を被保険者とした生命保険に加入するなど、自社株式を購入するための対策を講じておくことが重要です。
また、自社株式の売却には税金の問題が生じるため、特例の利用の検討が必要です。通常、非上場株式を第三者に売却した場合には「譲渡所得(売却益)」に対して一律20.315%の所得税・住民税が発生します。しかし、自己株式の取得の場合は「会社に蓄積された利益を株主に分配したもの」とみなされ「みなし配当」として課税されます。
みなし配当は、他の所得と合算した総合課税になり、他の所得が多ければ累進税率により税率が最高で55.945%(住民税を含む)になります。相続税の納税資金調達のための自社株式の売却であるのに、みなし配当による所得税が高額になってしまっては本末転倒です。
そこで、税務署ではこの問題を解決するために「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例」を用意しています。
この特例を利用し、一定の手続きを行うことで、みなし配当課税の適用がなくなり、譲渡所得として20.315%の税率にできるため、特例が利用できるかどうか必ず検討しましょう。
2-2.個人資産を換価して納付する
先代経営者の財産に換金性の高いものがある場合は、売却して納税資金に充てることが可能です。
不動産を売却して納税資金に充てるケースもありますが、売却先が決まるまである程度の時間がかかり、相続税の納付期限までに間に合わない可能性も考えられます。また、早く売却しなければならないことを知られると、足元を見られて不利な条件で売却せざるを得ない可能性もあります。
一方で、上場株式や投資信託商品、金などは容易に売却することができるため、納税資金の確保に効果的です。
2-3.銀行から借り入れて納付する
銀行から借り入れを行い、相続税を納付するという選択肢もあります。
銀行によっては相続関連ローンを用意しており、相続税の納付を目的として借り入れることができます。ローン利率は銀行によって様々ですが、次項で取り上げる「延納」の利率と比較しながら検討することをお勧めします。
2-4.延納制度を利用する
相続税が払えない場合は「相続税の延納制度(相続税の分割納付)」を選択できる場合があります。
延納利子税割合は年によって異なり、令和7年は0.9%になっていますが、相続財産に不動産が占める割合などによって利子税は異なります。
ただし、延納が認められない可能性もありますので、あらかじめ銀行にも相談しておくことをお勧めします。
2-5.物納制度を利用する
物納は文字通り、相続税を物で納付する制度であり、延納でも納付できない場合に認められる方法です。
物納の申請を行っても、延納ができそうだと判断される場合や、物納する財産が適当ではないと判断される場合には物納は認められません。
しかし、不動産を物納するよりも、不動産を売却した方が有利になるケースも多くあります。
3.自社株式の相続対策
ここまで、自社株式を相続する際に相続税が支払えない場合の対処法をご紹介しましたが、これらの対処法が必要とならないためにも生前からの相続対策が重要です。
3-1.自社株式の相続税評価額を下げる
自社株式の評価額は、会社の利益、純資産、配当の状況、資産の含み益・含み損など、様々な要素から算出されます。
評価額は、計画的に損失を出すなど、一定期間下げることも可能です。評価額を下げるために利用される主な方法は次のとおりです。
- 役員退職金を支給する
- 役員報酬を引き上げる
- 損金に計上できる生命保険に加入する
- 株式の配当を低く設定する
- 不動産を購入することで資産の組み換えを行う
3-2.自社株式の生前贈与
自社株式の相続税評価額を下げた段階で後継者に自社株式を生前贈与すると、低い評価額で贈与税が計算されます。
自社株式の評価額対策と生前贈与を組み合わせながら、生前にどれだけ多くの自社株式を後継者に移転できるのかが重要です。
また、贈与税の暦年課税の基礎控除(年110万円)を利用して自社株式を少しずつ贈与する方法もあります。ただし、この方法を利用する場合には、生前贈与加算の期間内に行われた贈与は、相続財産に加算され相続税を算出しなければなりません。
自社株式の相続税は当事務所へご相談ください
自社株式の相続では、生前から時間をかけて対策を行い、なるべく早期に後継者へ移転させることが大切です。対策を何も行っていない場合は、自社株式の評価額が高くなり、払えない額の相続税が生じてしまうこともあります。
後継者が相続税の納付で困らないように、早めに税理士に相談し、しっかりと時間をかけて相続対策を進めていきましょう。
当事務所は、相続税申告にも定評があり、自社株式の相続税対策もご相談いただけます。自社株式の相続でお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。