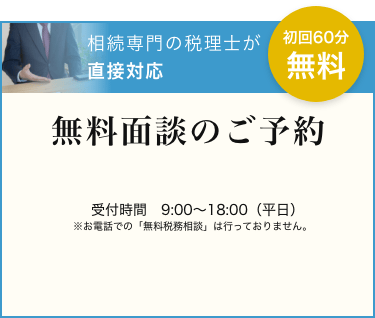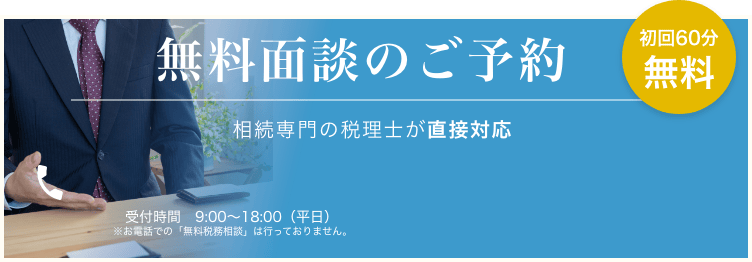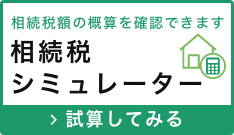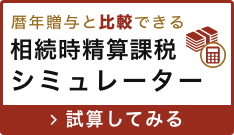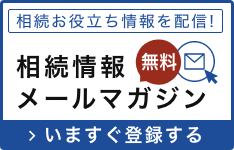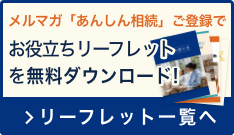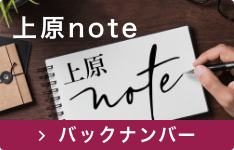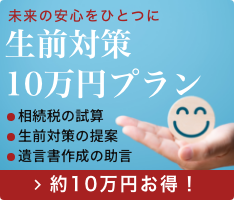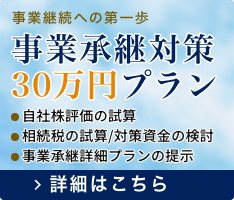目次
高齢化の波により、被相続人も相続人もご高齢になることが多くなります。相続人が認知症を患っているというケースもあるでしょう。相続人が認知症を患っていると、そのままの状態では相続手続きを進めることができず、特別な対応が求められます。
今回は、相続人が認知症を患っている場合の相続手続きについて詳しく解説します。
1.認知症で判断能力がない相続人は遺産分割できない
相続人に認知症の方がいる場合には、遺産分割をする際にどのように進めればよいのでしょうか。
1-1.判断能力がない者の法律行為は無効になる
遺産分割協議は、法律行為に該当します。遺産分割協議に参加して有効な合意をするためには、相続人自身に判断能力があることが必要です。
そのため、相続人の中に認知症で判断能力のない人がいる場合には、遺産分割協議に参加させることができません。遺産分割協議書に押印があったとしても、その遺産分割協議は無効とってしまいます。
1-2.判断能力がない者が法律行為をするには成年後見人が代理
認知症で判断能力がない相続人がいる場合には、成年後見制度を利用することによって、遺産分割協議を進めることが可能になります。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が著しく低下した人に代わって、財産管理や身上監護などを行う制度のことをいます。
1-3.成年後見人をたてるデメリット
成年後見制度を利用することによって、認知症の相続人がいたとしても遺産分割協議を進めることができるというメリットがありますが、成年後見制度には以下のようなデメリットも存在しています。
親族が成年後見人になれるとは限らない
共同相続人が成年後見人になった場合には、本人と後見人との間で利益相反が生じてしまい、特別代理人の選任が必要となります。
また、後見業務として遺産分割協議が予定されている場合には、親族後見人ではなく、弁護士や司法書士といった専門職後見人が選任されることも多々あります。
死亡するまで成年後見人は続く
遺産分割のために成年後見人を選任した場合には、遺産分割協議が成立したとしても成年後見人は辞任することはできません。
成年後見人は、判断能力のない本人の権利や利益を保護するために選任された人ですので、一度選任されると特別な事情がない限りは、本人が死亡するまで成年後見人としての業務を続けなければなりません。
費用がかかる
成年後見人制度を利用するためには、裁判所への申立て費用や弁護士費用などの負担が生じます。また、成年後見人には後見業務に応じた報酬が支払われるため、後見業務が何年も続くような場合には、本人の財産が目減りするというデメリットがあります。
成年被後見人の法定相続分以下での遺産分割はほとんどできない
成年後見人が遺産分割協議に参加する場合には、成年被後見人の法定相続分を確保する必要があり、成年被後見人の法定相続分を下回るような遺産分割協議を成立させることは原則としてできません。
そのため、相続税の配偶者控除の利用など相続税申告に有利な遺産分割内容にしようとしても認められない可能性が高くなります。
2.成年後見人をたてずにする相続手続き
以下のような方法をとることによって、成年後見人を立てずに相続手続きを進めることが可能です。
2-1.法定相続分どおりに相続
すべての相続財産を法定相続分どおりに分割する場合には、遺産分割協議は不要です。そのため、認知症の相続人がいたとしても相続財産を分けることが可能です。
しかし、相続財産に不動産が含まれている場合には、共有状態になるため、スムーズな不動産の売却が困難になることがあります。たとえば、不動産を売却したり、担保に入れたりする場合には、いずれも法律行為に該当し、判断能力のある共有者の同意が必要になります。認知症の共有者がいる場合には、判断能力がないため成年後見人を選任しなければ、有効な同意を行うことができません。また、預貯金も遺産分割の対象となるため、遺産分割が成立していなければ払い戻しに応じてもらえない可能性もあります。さらに、相続税申告に有利な分割内容にすることもできないといった数多くのデメリットがあります。
2-2.遺言書による相続
相続人に認知症の人が含まれている場合には、あらかじめ遺言書を作成しておくことによって、遺産分割協議をすることなく遺産を分けることが可能になります。相続人の負担を軽減するためにも、できる限り遺言書を作成しておくことをおすすめします。
ただし、遺言書は法律の要件を満たす有効なものであることが必要となります。また、内容も相続人の遺留分に配慮したものでなければ遺留分に関する争いが生じる可能性があります。
3.相続人が認知症の場合のポイント
認知症の相続人がいる場合には、以下のポイントを押さえておきましょう。
3-1.認知症のレベルを確認する
認知症といっても日常生活はほぼ自立してできるレベルから一人では生活が困難なレベルまでさまざまなレベルがあります。認知症と診断されたとしても軽度の認知症であれば、法律行為をするために必要な判断能力は存在しており、遺産分割協議を進めることは可能です。
そのためにも、まずは専門の医療機関を受診して認知症のレベルを確認するようにしましょう。
3-2.相続財産の確認
財産の内容によっては、相続財産に含まれず、遺産分割協議が不要になるものもあります。たとえば、生命保険の死亡保険金については、受取人が相続人に指定されている場合、相続財産ではなく相続人固有の財産として扱われることになります。
そのため、相続財産の内容や種類を確認して、本当に遺産分割協議が必要な財産であるかを判断しましょう。
3-3.遺言書を作成する場合
遺言書を作成することは、相続人に認知症の人がいる場合の有効な対策となります。しかし、遺言書を作成する人が高齢であった場合には、遺言書の作成能力について疑義が生じるおそれもあります。
このような場合には、証人が必要となる公正証書遺言を作成する、医師の診断書を用意するなどして、遺言書の有効性について疑義が生じないようにすることも必要です。
4.相続人に認知症の方がいる場合はご相談ください
相続人に認知症の人が含まれているという場合には、生前の相続対策によってトラブルを回避することが可能です。成年後見人の選任によって認知症の相続人がいたとしても遺産分割を行うことが可能になりますが、成年後見制度を利用することによるデメリットも存在しますので、将来の負担も踏まえて慎重に判断することが大切です。
認知症の方が含まれる相続手続きは、非常に複雑になりますので、少しでも不安があるという場合には、専門家に相談をすることをおすすめします。
当事務所では、相続税申告のサポートだけでなく、遺言書作成のサポートや、認知症になる前の対策として家族信託の支援も行っています。是非一度、ご相談ください。